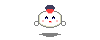 | 初めて行きました。法円坂のNHKの建物にくっついて立っているのですが、向かいの医療法人国立病院に行くたびに「何をしてるのかな?」と思いつつ、入ったのは初めてです。展示場は6階にあります。
1月25日〜2月7日まで「日本のわざと美」と銘打って、重要無形文化財とそれを支える人々の作品が紹介されていました。
陶器から織物、染め物、漆器あらゆる日本の手わざで作られる美術工芸品が展示されていて、江戸時代から脈々と受け継がれて来た物を一同に見る事ができました。
懐かしい近藤悠三先生の染付けの壷、まるで友禅の布を張り付けたかと思う程細やかな友禅柄を磁器に染め付けた富本憲吉の飾り箱、三輪壽雪の萩焼きどれもこれも欲しいものばかり。触る事もできないですが。
織物、染物も素晴らしい物ばかりでしたが、それを作る道具の精巧で美しい事。この道具、例えば染物の小紋や染縞、一寸(3.3センチ)の幅に千筋とか万筋といわれる線を染める型紙、伊勢型紙といわれるものですが、それを作る紙を漉く人、その紙にマクロサイズの錐で模様を彫る人、そんな裏方の手わざが守られていないと絶えてしまう工芸品です。
漆蒔絵につかう筆、蒔絵筆というらしいのですが、面取り筆よりも細くて、それでも毛を揃えて作るんですよ。蒔絵を描くのと同じくらいの器用さと根気がいると思います。苧麻から麻糸を引き出す技があって上布や縮みができる。
まだまだ色々展示されていました。この伝統を守って欲しいと思いますが、とにかく根気と我慢と清貧覚悟でないと守れないですから難しいです。
歴代の皇后は源氏丸とかいう蚕を育成されて、この日本産の上質な絹糸を吐く蚕を守られていますが、できれば皇室がこのような事に今以上力を注いで頂きたいと思います。美智子皇后もその前の皇后もそのような物に憧憬が深く興味もおありでした。着物を着る事にも抵抗を示されませんでしたが、次に皇后になられる予定の雅子皇太子妃はどうなんでしょう?ちょっと心配です。
|
No.1929 - 2006/01/27(Fri) 15:30:43
|